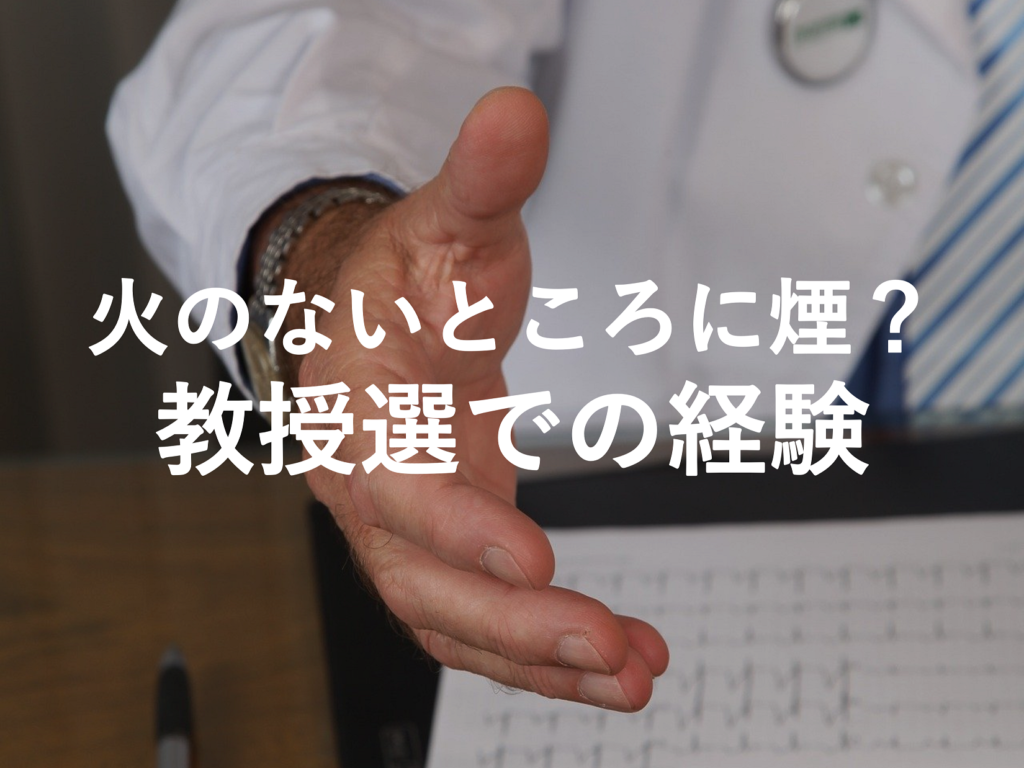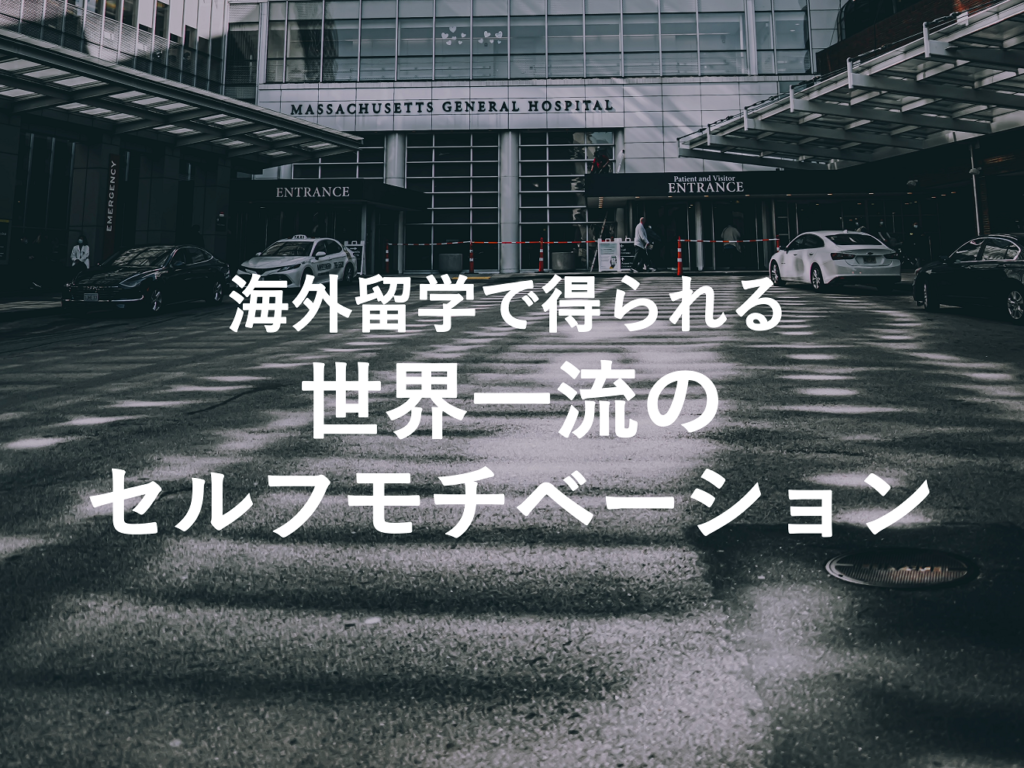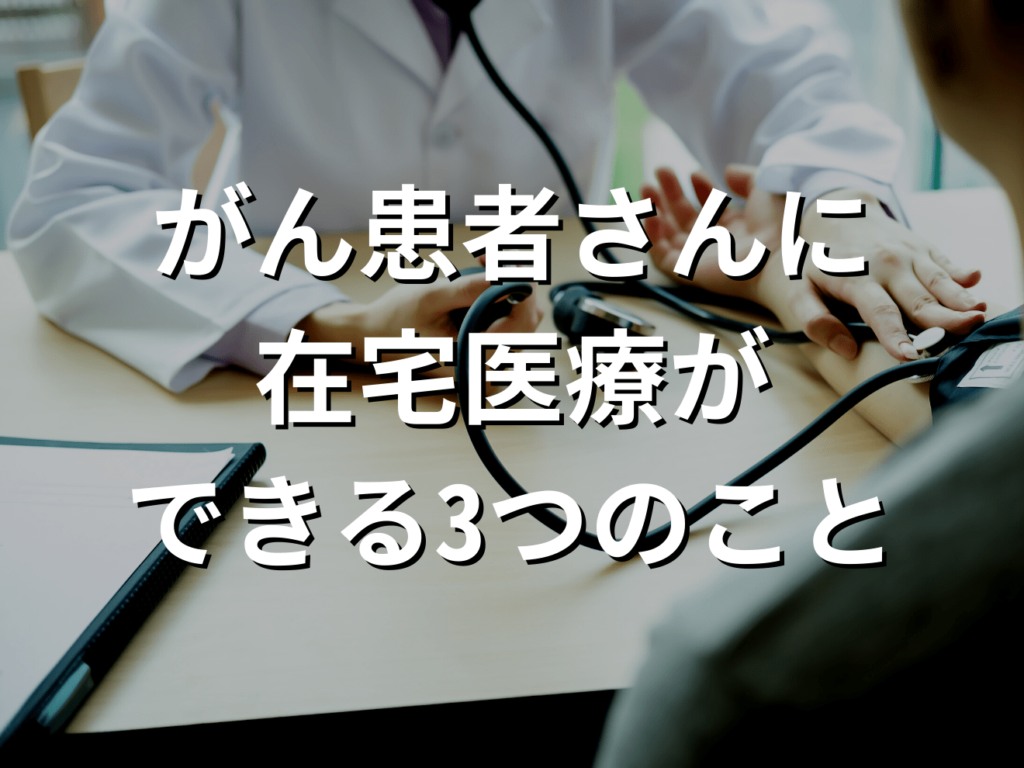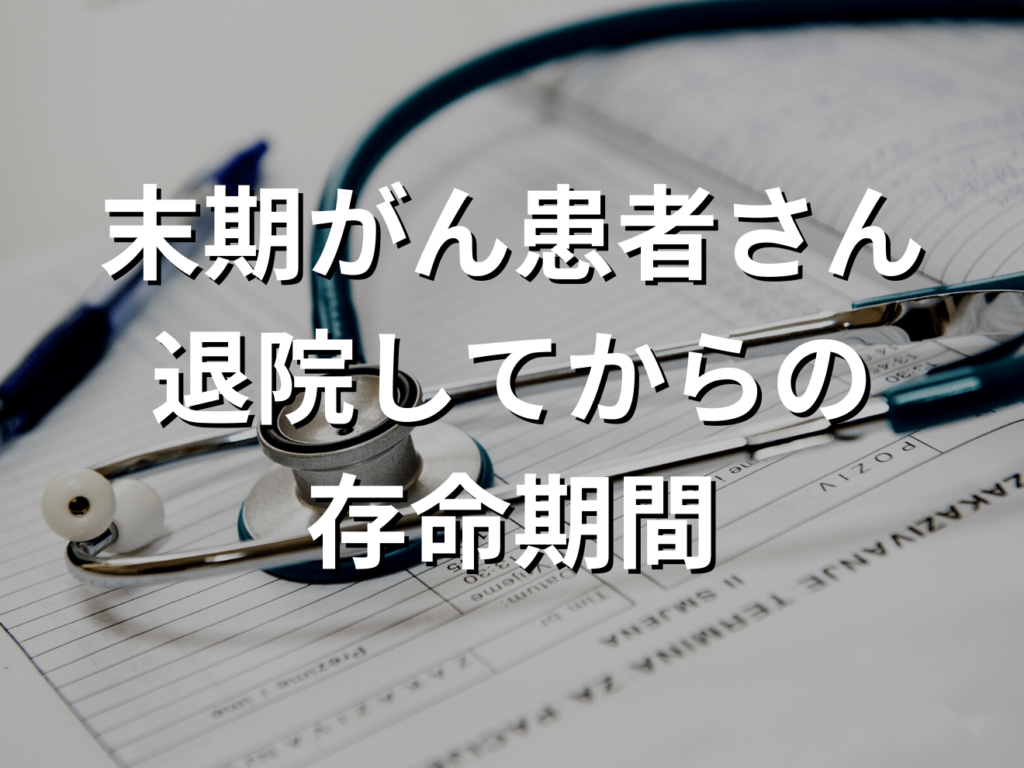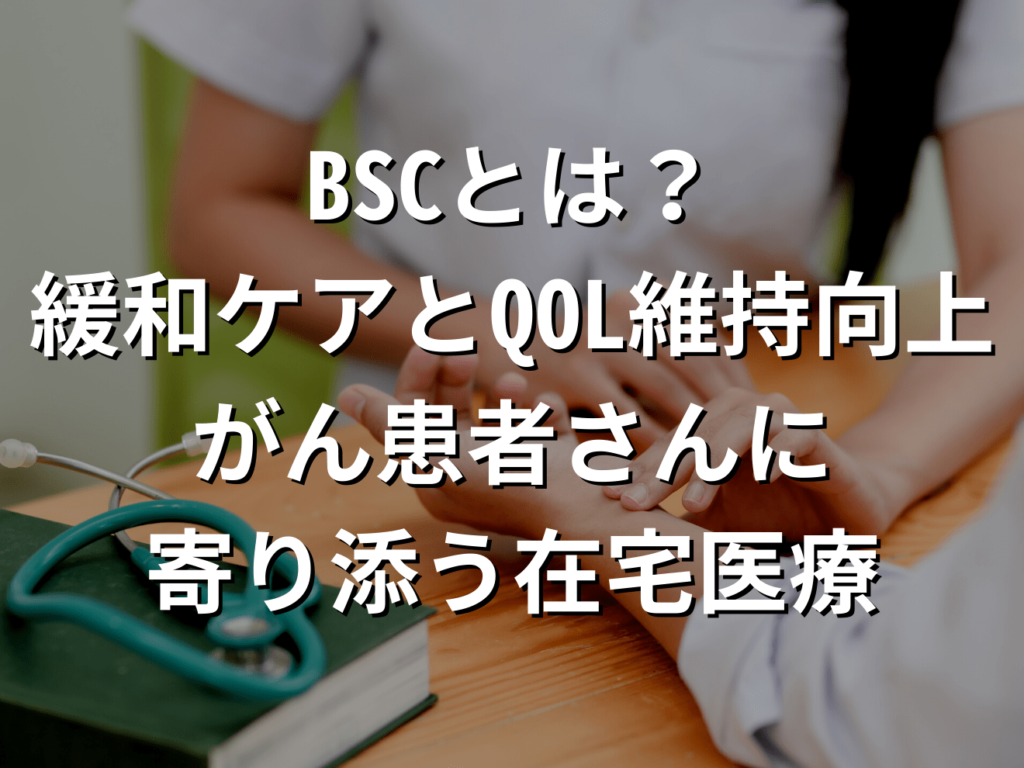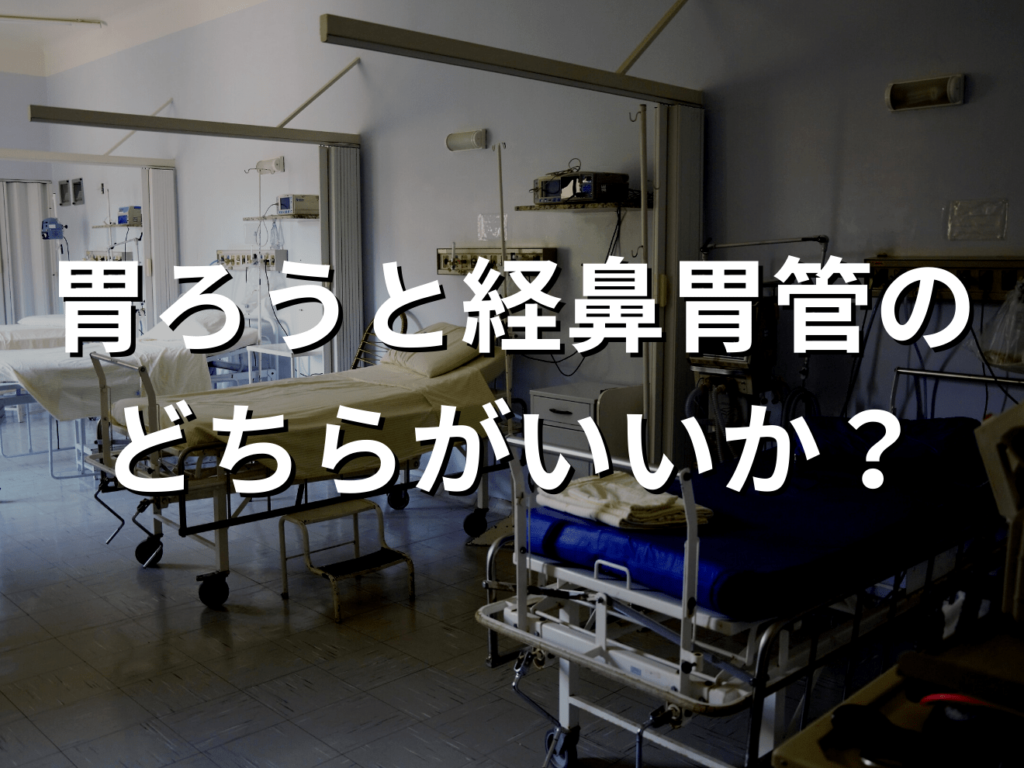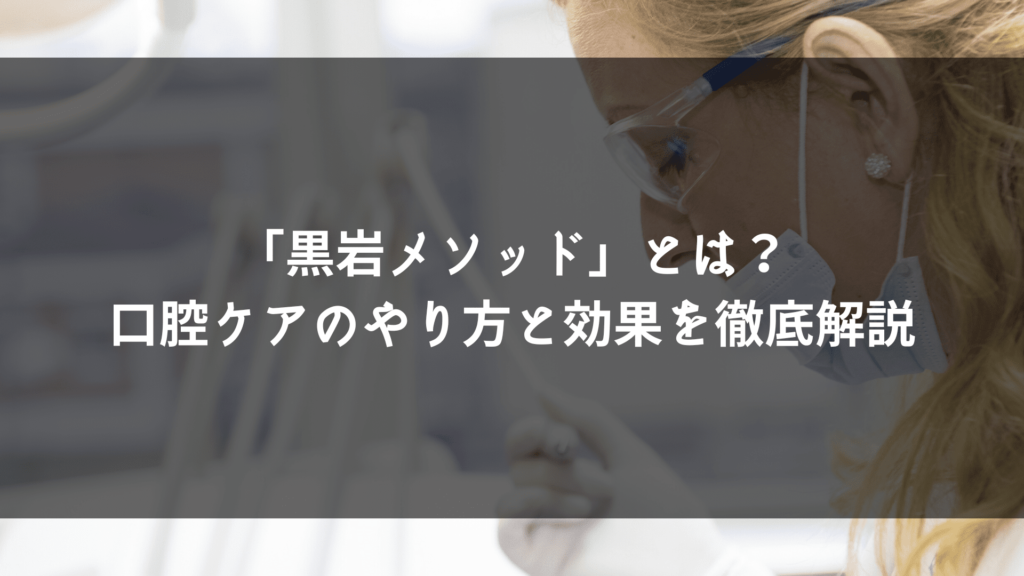末期がんの患者さんが退院してからの存命期間と自宅療養の選択

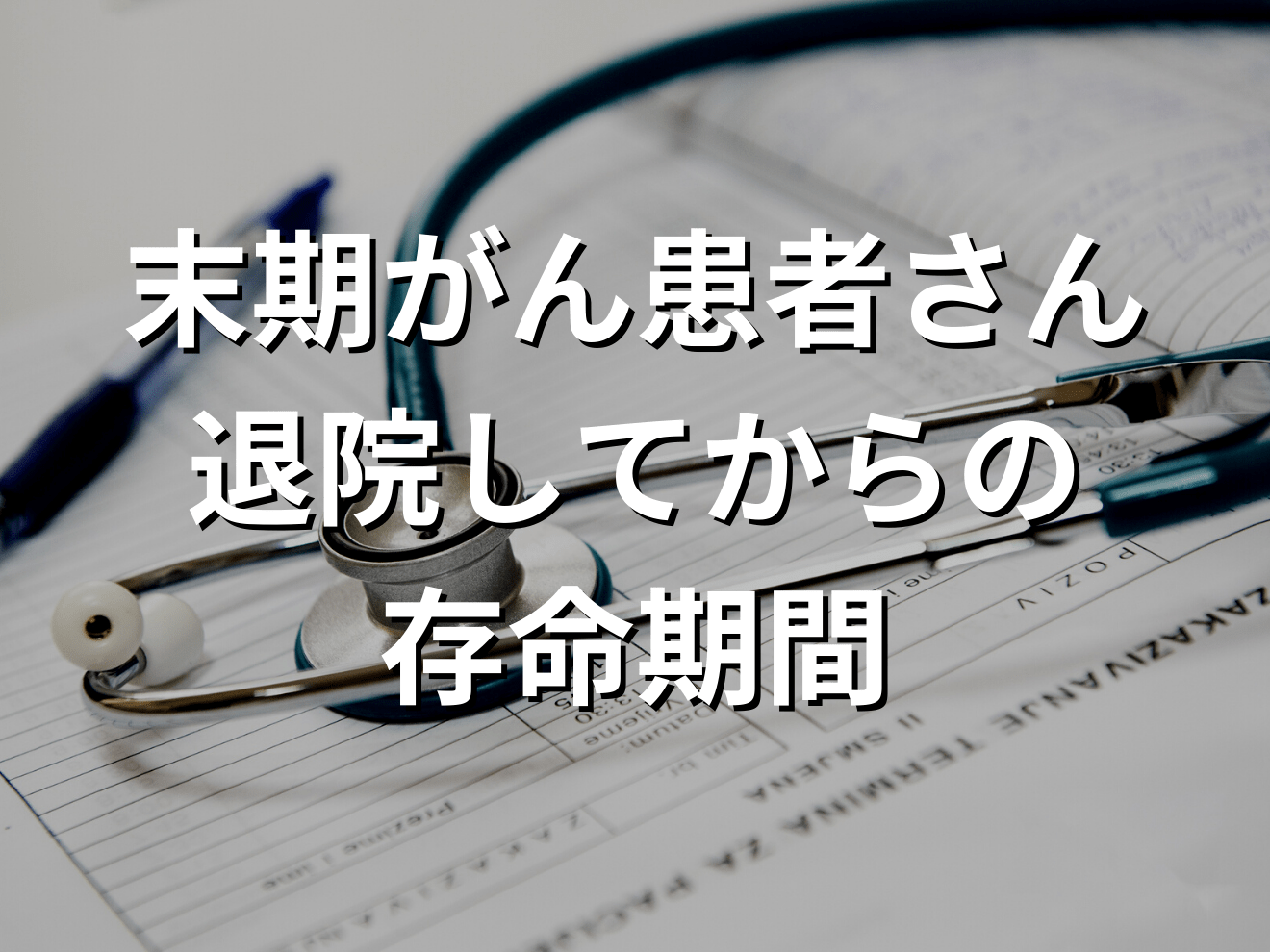
末期がん患者さんの「退院を早めた方がいいかもしれない」サイン
私が訪問診療を本格的に始めて数年たったころ、ある忘れられない出来事がありました。
ある日の退院調整会議、病院側から鈴木さん(仮名)の今までの経過と現在の状態について説明がありました。
90歳を超えるような女性で、約一年前に進行した胃がんが発見され、病巣そのものをとる手術は、病気の広がりと年齢を考えて無理だと判断。
病気の部分を避けて食事が通るようにと、胃空腸バイパス術が行われて、しばらく自宅で療養されていたところ、最近激しい下痢になり、腸炎と診断され入院したとのこと。幸い下痢も収まったので、まだ微熱があるものの、入院している必要がないし、もともとがんに対する治療は無理なので、退院し自宅療養にもっていきたいとのことでした。
そのような病院の医師からの話を聞きながら、鈴木さん宅の義娘さんもうなずいていました。ところが、退院調整会議が終わりに近づいたころ、その義娘さんが、「まだ熱があるので、下がるまで入院させておいていただけませんか?」と遠慮がちに発言されたのです。
それに対して病院の医師は「そうですね。それまで入院していてもいいですよ」と返しました。
退院調整会議が終わって、病室で休まれていたご本人にご挨拶しようと向かいました。案内されて病室に入ると、そこは二人部屋でしたが、鈴木さんおひとりが、カーテンが閉まって薄暗い部屋にやや上体を高くして横になっていました。
やや荒い呼吸で、じっと目を閉じていらしたのですが、「鈴木さん。あい太田クリニックの野末です」と声をかけると、目を開けて、少し私のほうに顔を傾けました。
「退院された後、ご自宅に伺って診察させていただきます」と続けたのですが、すぐに目を閉じてしまいました。私の話を理解されたのか、その前に声が聞こえたのかどうかさえ判断できませんでした。
この鈴木さんの様子を見て、私はかなり驚きました。「呼吸も荒いし、目も開けていることができない。もうそんなに長くないのではないか」と。
そして、病室を出た時に、義娘さんに「早く退院しないと、間に合わないような気がします。熱が下がるまで待たないほうがいいのではないでしょうか?」と伝えました。
私の話を聞いて、義娘さんははっとしたような表情になりました。そんなにすぐに亡くなってしまうほど危ない状態だとは感じていなかったようなのです。
自宅療養の選択による退院後の穏やかな時間
鈴木さんは、その退院調整会議から一週間後に退院し、私は退院翌日のお昼頃、鈴木さん宅に訪問診療に伺いました。
太田市の郊外の田園の中に1軒で独立して立っている築5年くらいの素敵なお家で、家の周りにはうずたかく薪が積まれています。
玄関のチャイムを鳴らして、ドアを開けると、3匹の小さな黒い犬が出迎えてくれました。私も、同行した看護師も、歓迎してくれているのかと思わず笑顔になりました。
退院調整会議でお会いした義娘さんに出迎えてもらって、玄関のすぐ脇にある、木の香りが満ちたフローリングのリビングに入っていきました。壁も木でできていて、薪ストーブが据えられています。大きく開かれたガラスの開口からは、眼前に広がる田んぼが見渡せます。
「こんなに素敵な家なら、退院して最期の時を過ごしたいという希望も当然だな」と思いました。鈴木さんは、そんな素敵なリビングに続く部屋の電動ベッドの上で静かに休んでいました。
もともとはダイニングとして使われている部屋です。そのベッドの傍らで、義娘さんは笑みを浮かべながら、昨日からの様子を語ってくれました。
その話によると、鈴木さんの退院後、ご近所や少し遠いところに住んでいる、本当に近しい親戚が入れ代わり立ち代わり訪れて、4時間近くも話し続けたそうです。そのあと、急に静かになったかと思ったらうわごとを一晩中言い続け、今朝になって、やっと静かに眠るようになったとのこと。
診察の際、呼びかけに対し、やっとうっすら目を開けるけれど、またすぐに閉じてしまい、声を出すことはできない様子でした。また、血圧は少し低めですが、100はあり、脈もしっかりしていました。ただ、おしっこがあまり出ていないとのことや、幸い痛みはないようだということなどがわかりました。
かなり弱ってきているとは思いましたが、昨日からの様子を聞き、「退院できてよかった」と思いながら、帰路につきました。
末期がん患者さんの退院後死亡率は3ヵ月以内に90%
すると、翌朝7時ごろ、鈴木さんの義娘さんから「呼吸が止まっているみたい」との電話が携帯にありました。すぐに伺うことを告げ、車で急ぎましたが、私の心には様々な思いが交錯していました。
「昨日感じたすぐにでもお亡くなりになってしまうのではないかという一抹の不安。どうしてそれをご家族に伝えなかったのだろうか。あまりに急なことで驚かれたのではないか。」「退院して、たった2日、自宅に戻ったことはよかったのだろうか?」「あんなに快適な家なのだから、もっと早く退院することはできなかったのだろうか?」
玄関で、3匹の子犬と、そして義娘さんの「ありがとうございました」という言葉で出迎えていただいたとき、私は思わず泣いてしまいました。
この末期がんを患った患者さんの物語はここまでです。この時から5年は過ぎているでしょうか。在宅医療を提供している医師の間では共通の認識ですが、いわゆるがんの末期状態で在宅医療に移行された方の存命期間は、一般に想像されている期間よりかなり短いものです。
あい太田クリニックのデータでは、退院して自宅療養に移ってから、お亡くなりになるまでの期間が10日以内の方が20%、1ヶ月以内の方が60%、3ヶ月以内の方が90%と、大変短いのです。
鈴木さんは、退院日を含めて3日、実質的には48時間も経っていないという、大変短いケースではありましたが、現在までのデータを振り返ると、それほど珍しいケースではないことがわかります。
この最後の自宅療養期間、短いことはデメリットばかりではありません。90%の方が3ヶ月以内にお亡くなりになるので、看病をするご家族が介護休暇を取る場合、介護休暇期間内に収まることがほとんどであるということです。
またご家族は、全身全霊をかけて介護されると思いますが、体力的にも、気力の面でも長く続けることには、かなりの無理があります。
このようなことを考えると、末期のがんで最期を迎えるときには、もっと積極的に病院を退院し自宅療養を選択されてもいいように思います。